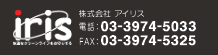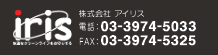それではここから、具体的な駆除作業の工程を説明します。
東京のねずみ駆除工事
 |
ねずみの追い出し作業について
天井裏をねずみが走りまわる物音が数カ月前から聞こえたり、台所や居間にねずみが出て来たりしている場合には、家の中にねずみが住みついているか、巣をを作っている可能性があると判断されます。
こうした場合には、『防鼠工事』をする前にねずみの追い出しを行います。『ねずみの追い出し作業』が必要かどうかの判断は天井裏や床下のねずみの糞の数の多少
、巣を作り易い環境かどうかで判断します。
|
追い出しに使う主なねずみ忌避剤
 ねずみ忌避用ゲルタイプ |
 ネズヤン |
 光り縄張り棒 |
 縄張り棒 |
 ねずみ忌避スプレー |
 |
侵入経路の遮断工事について
ねずみ駆除で最も重要な防鼠(そ)工事を確実に行う事によってねずみの再侵入は無くなります。
提出した見積書には、『防鼠工事する場所』と『工事の方法と使用する材料』が記載されており、その仕様書に基づいて防鼠工事を行います。
|
防鼠(そ)工事ってどんな作業?
防鼠(そ)工事には大きくわけて4つの作業があります。お見積調査の結果から、お客様のお宅の症状に合わせて適切な防鼠工事を行います。
| (1)コンクリート工事 |
ねずみの侵入口や通路をねずみの歯の立たないセメントを使った工事です。 |
| (2)板金工事・大工工事 |
鉄板、アルミ板、金網、木材、パンチングメタル等を取り付ける工事です。 |
| (3)吹き付け塗布工事 |
ねずみが寄り付かないハッカや唐がらし、ワサビ等の強烈な臭いのする防そ粘土や防そ塗料(ナラマイシン)の吹付け工事です。 |
| (4)殺鼠剤散布工事 |
床下や天井裏やねずみ穴に殺そ剤を散布したり注入したりする散粉工事等です。 |
 |

ねずみの捕獲作業について
ねずみの捕獲作業は以下のような状況で行われます。
1.追い出し作業後に、まだたくさん生息していると判断した場合
(飲食店や食品倉庫など)
2.追い出し作業が出来ない場所と判断した場合
(デパート、スーパー、大きな飲食店、ビル等)
捕獲には粘着シートを使用します。
室内1m2当たり0.5〜1枚使用した場合の平均的な捕獲率は約30〜50%です。3〜5日間継続して集中的に行いますと、生息するねずみの80〜90%近くが捕獲されます。
|
 |
|
 |
イエダニによる刺咬被害  一匹のねずみには約30〜40匹のイエダニが寄生して吸血しています。 一匹のねずみには約30〜40匹のイエダニが寄生して吸血しています。
このダニはねずみが死亡すると同時に四散して他の動物に移動します。建物内ではほとんどの場合人間に付着して吸血します。家人や従業員、来客に大きな被害が出ます。直径1㎝ほどの赤疹ができ、猛烈に痒くなり、4週間位続きます。
こうした二次被害を防止するために『粘着シートによる捕獲』を行います。 |
 |
 |
 |
 |
毒餌の設置と交換について
ねずみ駆除の最終段階で行うのが毒餌による駆除です。
これは『家屋内からのねずみの追い出し』や『粘着シートによる捕獲作業』を行った後で残っているねずみを完全に駆除するために行います。毒餌は毒餌皿に盛り、床下や天井裏、その他ねずみの通路等に設置し、7〜10日毎に点検し、新しい皿と交換します。
|
 |
効果判定と報告書の提出
効果判定
毒餌のねずみによる喫食は1回目、2回目とだんだん少なくなって来ます。『忌避剤によるねずみの追い出し』が充分な効果を上げていれば、ねずみにとってどんなにおいしい毒餌を用意しても、生息していなくなったのですから、全く喫食はありません。
家屋内から完全にねずみを追い出すことが出来ればそれが理想です。
※設置した餌が喫食されなくなれば、ねずみ駆除は完了です。
報告書の提出
最後にお客様へ『ねずみ駆除終了報告書』を提出します。
報告書には、いつ、どんな材料を使ってどんな工事をしたか、ねずみの追い出し効果や、毒餌の喫食の状況はどうだったか等が記載されます。
|
 |
年間管理契約について
アイリスでは、見積の段階で、建物の構造上の問題や利用状況などの理由から、完全駆除が難しいと判断した場合、その事をしっかりとご説明した上で駆除対策を提案致します。駆除後はねずみの再発生率(復元率)を低めるための厳しい基準(※1)を定め、その基準に従った定期点検調査を行います。
※1:IPMを取り入れた有害動物群管理システムによる再発防止管理をご参照ください。
|